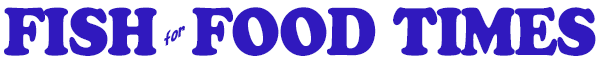
�悤���� FISH FOOD TIMES ��
����27�N 4�����@No.136


�n�}�_�C�̍��t�����t���ؐg
�����a���n�}�_�C�Ƃ������́A����Łu�A�J�}�`�v�ƌĂ�A�����n���ɍs���Ƃ悭�����u�A�J�}�c�v�Ƃ������ɂȂ�A�֓��ł̓I�i�K�A�X�ɑ��̂���n��ł́u�w�C�W�v�ȂǂƂ��Ă�Ă���Ƃ������Ƃ��B
���̃n�}�_�C�Ɨǂ����Ă��Ă���̂����̉E�摜�̋��ł���B
�摜����ׂ�ƃn�b�L���Ⴂ�������邯��ǁA���ꂼ���ʂ̏ꏊ�Ō���Ƃ��������ǂ���Ȃ̂���u���f������قǂ�������ł���B
 �@
�@
����̉摜������n���Łu�A�J�}�`�v�ƌĂꔒ�g�̍������Ƃ��Ĉ�����u�n�}�_�C�v�ł���A�E�̂悭�������͑���I�ɂ��̔����ȉ��̉��i�ł��������邱�Ƃ̂Ȃ��u�n�`�r�L�v�Ƃ������ŁA�n�����͉���Ń`���E�`���E�I���������ł̓A�J�{�ƌĂ�Ă���B
�n�}�_�C�̓X�Y�L�n�X�Y�L�ڃX�Y�L���ڃt�G�_�C�ȃn�}�_�C���ł���A����X�̋�����ł͉��̉摜�̂悤��1��2,200�~�Ƃ������������������Ă�������ǁA���̉��i�͂��̓��������ʍ����Ƃ����̂ł͂Ȃ��A���̂��炢�̔��������ʂɒʗp���鋛�ł���B
�n�}�_�C��������t�G�_�C�Ȃɂ̓t�G�_�C���A�q���_�C���A�A�I�_�C���Ȃǂɕ�����A��30��ނ��̂�������̐e�ʌZ�킪���݂��Ă���B

�����ۂ��X�Y�L�n�X�Y�L�ڃX�Y�L���ڃn�`�r�L�ȃn�`�r�L���̃n�`�r�L�́A���̑�����n�`�r�L�Ȃɂ͑��ɂ���Ƃ������Z��e�ʂ͂قƂ�ǂ��Ȃ��Ƃ����Ⴂ������B
��{�Ƃ��ăt�G�_�C�Ȃ̋��B�͔��g�����A�n�`�r�L�͐��̂悤�ɐg���Ԃ��̂������ŁA�ȉ��̉摜�̂悤�ɂ܂�ŃJ�c�I��}�O���̂悤�ɐԂ��ۂ��g�����Ă��邯��ǁA�s�v�c�Ȃ��Ƃɂ��̋��͔��g�̔��e�ɕ��ނ����Ƃ������Ƃ��B

�������h�g�ɂ���ƈȉ��̂悤�ɂȂ�A�g�̐F�͂܂�Ő��̃J�c�I�̂悤�Ɍ����Ȃ����Ƃ��Ȃ����A�n�`�r�L�̓J�c�I�ł��Ȃ��n�}�_�C�ł��Ȃ��̂ŊԈႦ�Ȃ��łق����B

�����Ĉȉ��̉摜�̓n�}�_�C�ł���A��̉摜�Ɣ�r����Ɛg�̐F�̈Ⴂ�����m�ɕ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
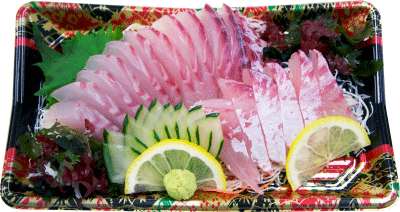 �@�@
�@�@
4������5���̓n�}�_�C���Ă̎Y�����}����O�ɃZ�b�Z�Ǝ��b��~���Ă��鎞���ł���A���Ƃ��Ɣ牺���b���������ł͂Ȃ��T�b�p���n�̃n�}�_�C�́A���̋G�߂ɂȂ�Ƃ܂�ŗ{�B��̂悤�ɁA�V�R���Ƃ͎v���Ȃ��قǓ������b�𗭂߂Ă͂��邯��ǁA���̖��͗{�B��̂悤�ɃM�g�M�g�Ǝ����������̂Ƃ͈���Ă��āA�V�R���炵�����̏��������邱�Ƃ��o����̂ł���B
���̂悤�ɖc��������b�̎������m�F���邾���ł��A���̋G�߂̓n�}�_�C���N�Ԃň�Ԕ������������ł��邱�Ƃ�������̂����A�n�}�_�C����������H�ׂ�ɂ͏�摜�̂悤�ɔ疳���ł̃I�[�\�h�b�N�X�Ȏh�g�̐H�ו������ł͂Ȃ��A���摜�̂悤�ɑN�₩�ȐԂ��F�̔���ꏏ�ɐH�ׂ�u�đ��Z�@�v�����p�����h�g�������߂ł���B

�đ�������ɂ͏����ł��ڂ������炢�ɂ��������t�������������������킦��B

���g����w�ƕ��ɕ����āA��ڂ̕����甖����ɂ��Đ���t����B
���ăn�}�_�C�͎h�g�Ŕ������������łȂ��A���̑��Ɏϕt�������̂Ȃǂɂ��K�����������̍ޗ��ƂȂ�B
���̉摜��5�s�ȏ�̑傫���ɂȂ邱�Ƃ��������Ȃ��n�}�_�C�Ƃ��ẮA��r�I���^��700�c�O��T�C�Y�̔��g���A�X�ɔ������ŏ��i�ɂ������̂ł���A�����摜�͂������ď��i���������̕Њ���Łu4����1�g���v��t���Ă���B

�n�}�_�C�͔��g�̍������Ȃ̂Ŏd���ꉿ�i����r�I�������Ƃ��Ƃ܂��A��摜�́u4����1�g���v�ŏ��i�ɂ����̂����A�����������i�Ŏ�ɓ��邱�Ƃ�����Έȉ��̉摜�̂悤�ɔ��g���̏��i�Ƃ��Ă��ǂ����낤�B

������4����1�g���Ɣ��g����t�����ؐg���i�̂��ꂼ��́A���Â�����t���̕��̕Аg���g���Ă���A�����������ɂ����������J�}�t���ňꏏ�ɓ��ꍞ��ł��邱�Ƃ����̋��ʍ��ł���A����͈Ӑ}�I�ȍl�����Ɋ�Â��Ă���B
���Ȃ��̕��̔��g�ɂ��ẮA�O�f���Ă�����Ȃ��h�g�Əđ��h�g�̎h�g�p�ޗ��Ƃ��Ċ��p���Ă���A1�����h�g�p�Ŕ����A�����Đؐg�p�ɔ������ŗ����̏��i�ւƓW�J���邱�Ƃ�O��Ƃ��Ă���̂��B
����͋�1���������ʂ̉��l�̏��i�Ƃ��Ĕ̔����邽�߂̎�@�ł���A�������邱�Ƃ�SKU���g�����ċ�����̖��͂��������ƂɂȂ邩��ł���B
�܂��ؐg�̏��i�ɂ͂ǂ����������ꍞ��ł��邪�A����������邱�ƂŃ{�����[�����𑝂��Č��������Ƃ����l������͂��邯��ǂ��ꂾ���ł͂Ȃ��B
��ʓI�ɋ��̓����̓^�C��u���Ȃǂ̈ꕔ���O�Ƃ��ĉ��l�̂Ȃ����ʂƂ��đe���Ɉ����Ă��āA�e�i�A���j�Ƃ������̂œO���̉��i�Ŕ�������Ă���B
�������O���ł������ɂȂ�̂͂܂����������ŁA���ɂ͔p�����Ƃ��Ďc��e��ɂ��̂܂̂Ă��Ă���̂����X����̂������ł���A����������Ȏ��Ȉ���������̂ł͂Ȃ�����Ȃ�̉��l��F�߂��������Ƃ����ړI������̂ł���B
���͖��X�`��ϕt���A��Ȃǂɗ�������A�g���炾���ł͂Ȃ����̍�������ł�|�������ɂ���ďo�`���o�Ĕ��������Ȃ�̂����A�����́u�q�������̍���������v�Ƃ������R�Łu���̂��鋛�����v���h������鎞��ł���A���̏�Ȃ������ɂ܂�Ō}�����邩�̂悤�ȁu���̍��Ȃ��ؐg�v�Ƃ��̍H�ꐻ�i���o����Ă���悤���B
�{���͋��̓����̊ዅ���ɂ��鎉�b�ɂ́ADHA��EPA�������܂܂�Ă��邵�A�����Ƀ[���`�����̑������ɂ̓R���[�Q���Ȃǂ��������Ƃ���A���̃A���𖡑X�`�Ȃǂɂ��č������c���ĐH�אs�����Ƃ����������́u�����\�S�Ɋ������v�Ƃ����Ӗ��ł͍ō��̐H�ו����ƌ����邾�낤�B
�M�҂�����܂łɐH�ׂ��u���̖��X�`�v�ň�ԋL���Ɏc���Ă���̂́A2008�N10��29���̒��ɐΐ쌧�̕X�����`�ŐH�ׂ��u���Ԃ��`�v�ł���B

�X�����`�̒��ɂ���C���H���͋��s��]�ƈ�����ȋq�Ƃ��ĉc�Ƃ��Ă���X�ł���A��摜�̂��Ԃ��`�͕X�����`�̖��������ƂȂ��Ă���B
���Ԃ��`�Ƃ́A�H���̕ǂ̌f���Ă���Ŕ�����ƈȉ��̂悤�ȗR���̂��̂炵���B
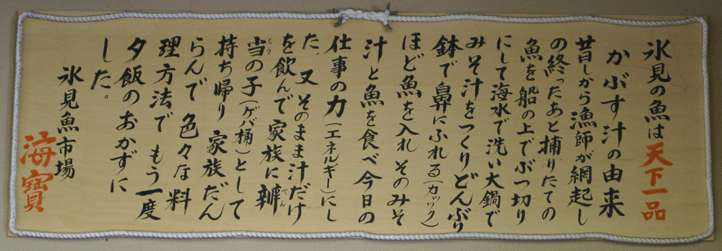
���������R���̂�����̂Ȃ̂�����A���Ԃ��`���u���̃A�����X�`�v�Ɠ������ƌ����Ă��܂��Ɠ{������ƂɂȂ邩������Ȃ����A���̎��M�҂́u�A�W�A�M���T�o�A�J�}�X�A�`�R��A�X�����C�J�Q�\�A���^���K�j�ȂǁA�Ԃ�̋����S�����S�����Ɩ��X�`�̒��ɓ����Ă��āA�܂��ɍ����Ȗ��������v�ƁA���̐H��̊��z���L���Ă���B
���Ԃ��`�̒��g�͋��̃A���Ƃ��ł͂Ȃ��̂͂�������A���̑��݈Ӌ`�Ƃ����̂́u���̃A�����X�`�v�Ɖ���ς����̂ł͂Ȃ��A����͎���Ȍ������ɂȂ邩������Ȃ����A���ۂɐH�ׂ����G�͖{���Ɂu�����悤�Ȃ��́v�������̂ł���B
�X�����`�Ƃ��Ԃ��`�̂��Ƃ�FISH FOOD TIMES ��59 �t�N���M�p����i����20�N11���j�̒��ł��G��Ă���̂ŁA�������̂�����͂�������`���Ă݂Ăق����B
���āA���Ԃ��`�̂悤�ɗ��h�ȋ��̍ޗ����g�������̂ł͂Ȃ��A�h�g��ؐg���m�ۂ�����Ɏc�鋛�̃A�����g���ċ��̃A�����X�`�����|�C���g���A�ȒP�ȕ\�ɂ܂Ƃ߂Ă݂��̂ł���܂ł����ɂ��܂艏���Ȃ��������͈�Q�l�ɂ��Ăق����B
| ���̃A�����X�`�̍����|�C���g | |
|---|---|
| �P | �����͓K�x�ȑ傫���ɐ�B�A�S��G���u�^�̕����͎g��Ȃ� |
| �Q | �q�����c���Ă���A�L�݂��o��̂Ő藎�Ƃ� |
| �R | ������L����S��������A���Ő���Č��≘��𗎂Ƃ��Ďg�p���� |
| �S | ���~��ɂ��ĉ���𗎂Ƃ��L�݂� |
| �T | ���𗬂������ɂ��Ďc�����E���R�⌌�t���������A������x����𗎂Ƃ� |
| �U | �e�M���Ƃꂽ��U���������Đ��C��� |
| �V | �␅�ɃA�������Đ�������M���A�ЂƎϗ���������ɉ���߂� |
| �W | �L�݂��o�����|�݂������o���ׂɁA�����Ă��鋛�̃A�N�J�Ɏ�菜�� |
| �X | ���ɂ�����̂܂܁A��������Ǝ|���Ǝ��������o�� |
| 10 | �Ō�ɖ��X������B���X�����Ă���͕��������Ȃ� |
 |
|
������������H�ׂ�ɂ́u���̍�����������悤�ȐH�ו��v�ւƓ�����̂ł͂Ȃ��A���̃A���̖��X�`�̂悤�Ɂu������o��|���������������v�����̕��Ɍ��������Ƃ��d�v�Ȃ̂ł���B
���������̓��{�ɂ����ẮA���́u�|���v�Ƃ������Ƃ���������Ɨ�������Ă��Ȃ����Ƃ���A���������u�t�@�[�X�g�t�B�b�V���v�ȂǂƏ̂����A�H��Ő��Y���ꂽ���ՂŊȕւȏo���������i�ɐU��������ւƁA���{�̏���҂͌����킳��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv�����̂�����B
���������u�|���v�Ƃ͉�����H�@�Q�l������R�����Ă݂�ƁE�E�E
����100�N�ȏ���O�ƂȂ�1908�N�ɁA�����鍑��w�����̒r�c�e�c�͍��z�o�`�̂��������̐��̂̓O���^�~���_�ł��邱�Ƃ����A�Ö��E�����E�_���E�ꖡ��4�̊�{���ł͐����ł��Ȃ����̖����u5�߂̊�{���v�Ƃ��āu�|���v�Ɩ������A���̃O���^�~���_���听���Ƃ��钲�����̐������@�ł̓������擾���A1909�N5���ɂ͎|���̒������ł���u���̑f�v����ؐ��i���̖��̑f������Ёj���甭�����ꂽ�B
�����ł͉p��ɂ��́u�|���v��\�����t���Ȃ����߁A���ۓI�Ɋw�p�p��Ƃ��āuumami�v���g����悤�ɂȂ��Ă��邯��ǂ��A�����1980�N��ɂȂ��āu��Ɏ|���������������g�D������v���Ƃ��킩��A����Ɓu��5�̖��o�v�Ƃ��Đ��E�I�ɔF�߂���悤�ɂȂ������̂ŁA�|������������Ă����80�N���̒����ԁA���Ă̌����҂����́u�|���v�Ƃ����̂�4�̊�{�̖��o�̒��a�Ƃ��ĕ\��銴�o�ł����Ċ�{�̖��o�ł͂Ȃ��Ƃ��Ă����̂������B
���{�����ɂ����Ă͍��z�ŏo�`���Ƃ�����ɃJ�c�I�߂ŏo�`���Ƃ邪�A����͍��z�̃A�~�m�_�n�O���^�~���_�ƃJ�c�I�߂̊j�_�n�C�m�V���_�Ƃ����킹��ƁA���ꂼ�ꂪ�P�Ƃ̎������͂邩�ɋ����|����������悤�ɂȂ�Ƃ��������l�̌o���l���炫�Ă���̂ł���B
�܂�C�m�V���_���L�x�ȋ��ƃO���^�~���_�𑽂��܂ލ��z��ő��̃O�A�j���_�Ȃǂ̐A�����H�i�����킹�ė�������Ǝ|�������ɋ��܂邱�ƂɂȂ�A�|���Ƃ����̂͑��̊�{���ɔ�ׂ�Ɩ������₩�ŁA�����������㖡�������̂������ƂȂ��Ă���B
���{�l���̂��疈���H�ׂĂ������X�`�Ƃ����̂́A�������̃C�m�V���_���L�x�ȃC���R�ƐA�����̃O���^�~���_�������Ղ�܂܂�Ă��閡�X�����R��̂ƂȂ��āA���̔������������o���Ă���̂ł���B
���̃A�����X�`�Ƃ����̂́A�����̖��X�`�̒��ŃC���R���\�ɏo�Ă��Ȃ��B�ꂽ���Ƃ���Ȃ�A���̃A���̓C���R�Ƃ͋t�Ɂu�\�ɏo�Ă�������v�ƂȂ��Ă���̂��Ⴄ�Ƃ���ł���A�������̃C�m�V���_���L�x�ȃA���ƐA�����̖��X�̃O���^�~���_����]�t�]�����`�ƂȂ��Ă��邾���Ȃ̂��B
���X�`�̔������������o�I�ɗ������邽�߂Ɉ�Ԏ����葁�����@�́A�o�`�̎|���Ƃ��������̃x�[�X�ƂȂ��Ă��Ȃ����Ă̍��ւP�T�Ԉȏ㗷�s���A���̊Ԃ����������X�`�Ȃǂ̓��{�H��H�ׂ��A�A�����������̎���ł����ʂ�̖��X�`������ł݂邱�Ƃ��B
��̏�Ŗ������݂��߂�悤�ɂ��Ȃ��疡�X�`������A���Ԃ�u���X�`���Ă���Ȃɔ������������̂��E�E�E���܂��I�v�Ɗ�������͂��ł���B
���������u���܂��I�v�ƌ��킹�邽�߂ɂ́A�������|�����������Ɉ����o���Ă�邱�Ƃ��K�v�ł���A���̂��߂ɂ͋��̂��Ƃ�ǂ��m�炸�ʓ|�Ȃ��Ƃ���肽����Ȃ�����҂̃j�[�Y�Ɍ}�����邱�Ƃ�����l����̂ł͂Ȃ��A�{���ɋ�����������H�ׂ�ɂ͂ǂ�����Ηǂ������A����葤������҂ɋ����Ă����邱�Ƃ��d�v�Ȃ��Ƃł͂Ȃ����Ǝv���B
�t�@�[�X�g�t�B�b�V���ȂǂƂ����u����҂̋�����v�͓��X�̗�����S����w�Ȃǂ�ӑĂɂ��邾���ł���A���̖{���̖���m�邱�Ƃɂ͂Ȃ����Ă����Ȃ��Ǝv���A���̂悤�ȁu���H���y�ւ̖�D��v�Ƃ����̂́A���ʂƂ��Đ�X�̋��̏���A�b�v�ɂ͌��т��Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƍl����B
����ɋ���̔����锄��葤�ɂ��Ă��A���̐ؐg��100�~�Ȃǂ̈������i�Ŕ���悤�Ȃ��Ƃɓ����g���̂ł͂Ȃ��A���̓��ɂ����p���l�����邱�Ƃ����q�l�ɒm�炵�߂邽�߂ɂ͂ǂ�����Ηǂ����A�Ƃ��������Ƃɂ������g���Ăق������̂ł���B
��Ɉ��肵��������ւ鋛�̔ɐ��X�Ƃ����̂́A���̒��̌i�C���ǂ��Ȃ낤�Ƃ��ڐ�̈����ňꎞ�I�ȖA����������悤�Ȃ��Ƃ����A�����I�Ɉ��肵������������炵�Ă����ڋq��͂ނ��߂ɁA���������͍����Ă��i���̍������i��n���ɒ���u�{���u���̏����v���R�c�R�c�Ƒ����Ă���Ƃ��낪�����悤���B
�u�{���u���v�Ƃ͌����č����Ƃ������t�Ɠ����Ӗ��ł͂Ȃ��A���̓����A�������_�ɂ͂��Ȃ����p�̏p����{�Ƃ��Ēm���Ă��āA��������q�l�ɋ����邱�Ƃ̏o����m�E�n�E������A����ł͎��ۂɂ�������i�Ƃ��ĕi�������Ă���悤�ȓX�̂��Ƃ������̂ł͂Ȃ����낤���B
�������Ȃ��̓X�̂��q�l�����̖{���̖���m��Ȃ��悤�Ȑl�������悤�ł���Ȃ�A���̂悤�Ȃ��q�l�ɑ��Ċȕւň��Ղȃ��[�J�[�̏o�������i�������߂���̂ł͂Ȃ��A�N�x�̗ǂ��{�̋��ł���Ȃ���A�i���̍����{���u���̋���i�������āA���̏��i�̗ǂ������q�l�֒n���ɃR�c�R�c�Ƌ����Ă������Ƃ��d�v�ł���A���̂悤�Ȑ₦�ԂȂ��w�͂Ƃ����̂���X�ɑ傫�Ȕ���ւƂȂ����Ă������Ƃł��낤�B
FISH FOOD TIMES �͂��̂悤�ȓw�͂��d�˂�l�B�̂��߂ɁA���̖����̈�[������`���o����Ǝv�����̂ł���B
| �X�V�����@����27�N 4�� 1�� |
�H�i���Ɗ�e��
| �H�i���Ɗ�e���i�������j |
���ӌ��₲�A���͂�����܂� info@fish food times

